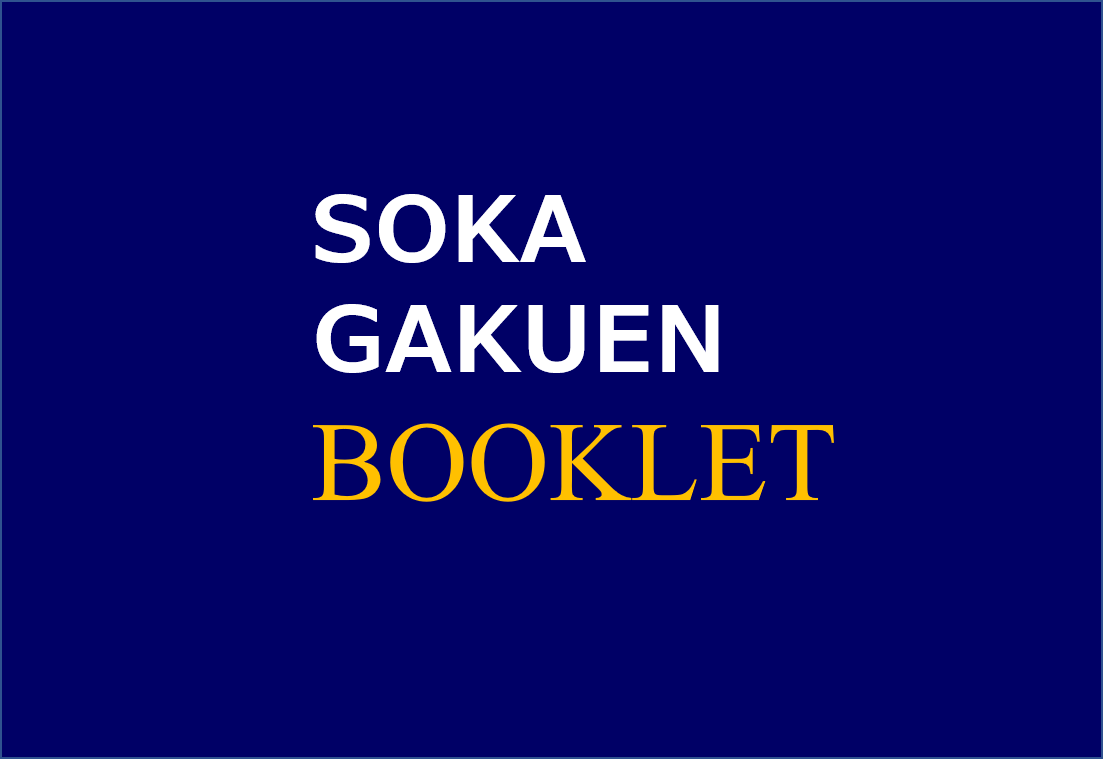
SOKA GAKUEN BOOKLET
「子どもは遊びの天才である」――。
授業中の教室から、楽しそうな児童の声が響いてくる。
遊びが児童の学びをひらくと信じる東京創価小学校の日常風景だ。
現在教育現場で注目されている“遊びを通した学びの実践”。
東京創価小学校では遊びを通した学びを実現するカリキュラムの実現に挑戦している。
遊びを通して友情が深まる。
そして、その友情は学習の場面でも必ず活かされる。
一方で、授業で学んだことが新しい遊びのアイデアを生み出すこともある。
「学び」の未来をひらく「遊び」の力。
東京創価小学校の遊びの世界に飛び込んでみた。

遊び=学び?
小学校において、遊びが本当に学びになるのだろうか?
そんな疑問を打ち砕くのが、遊びを学びに直結させたカリキュラムの数々である。
2年生では生活科で行う「おもちゃ祭り」、3年生では総合的な学習の時間を活用した「学年お祭り企画」、そして4年生では「asobiゼミ」という形で、発達段階に応じた
取り組みを展開している。
さらに全学年を通じて実施する「フレンドリー活動」では、1年生から6年生までの
異学年の児童が1つのグループになり、学年を超えて協力し遊びを企画する。
これらの活動は、子どもたちが自然に協力し合い創造力を発揮する「学びの場」と
なっている。
自己肯定感を育むasobiゼミ
東京創価小学校の遊びを通した教育の中でも、特に注目されるのが4年生の「asobiゼミ」である。この取り組みは、 「小4の壁」と呼ばれる成長過程での課題に着目し、子どもたちの自己肯定感とコミュニケーション能力の向上を目的として始まった。
asobiゼミで決められている唯一の条件は、「4つのルール」を守ること。
このルールを守るなかで学び、育まれる力がある。
asobiゼミの4つのルール
①「いいね!」「なるほど!」が合言葉
②失敗も学び すべてを楽しもう
③みんなで考え、みんなで楽しむ
④一人も置き去りにしない

遊びと学びの循環で生まれるもの
東京創価小学校では、子どもたちが低学年モットー「明るい子・思いやりのある子・ねばり強い子」として育つよう、遊びと学びを大切にしている。その中で、遊びの場もまた、友だちとの学びの場となる。教員は、asobiゼミでの経験を次のように語る。
「asobiゼミ」で泥あそびをした時、最初はそれぞれが思い思いに砂の山を作っていました。
でも、2つの山を作っているグループが、それぞれの山をつなぐ道を作ったらもっと楽しくなるのではないかと考え始めました。そこから「水を通せば川になる」「トンネルも作れる」と、子どもたちの発想がどんどん広がっていったんです。自然と「もっと良くしよう」という協力の輪も広がり、まさに「思いやりのある子」の心が芽生える瞬間でした。「バケツが必要」「もっと大きなスコップを持ってきて!」といった声が飛び交い、授業中の教室ではなかなか見られないような、笑顔と創造力に満ちた時間となりました。この創造力は、課題を見つけ、考え、判断し、問題を解決する力に繋がっています。
子どもたちの振り返りアンケートでも、「今まで話したことのない子と仲良くなれた!」「失敗を恐れずに挑戦できるようになった!」「協力して遊びを作り上げる楽しさを知った!」といった声が多く寄せられました。これは、遊びを通じて「ねばり強い子」としての挑戦する心と、「明るい子」としての友情を育む喜びが、自然に育まれている証拠だと感じています。
東京創価小学校の子どもたちは電車通学生が多く、地元で自由に遊ぶ時間が限られている子も少なくありません。だからこそ、学校で行う遊びの時間がより重要だと考えています。普段の授業で大切にしている「学び合い」と同様に、授業の中に遊びを取り入れることで、子どもたちが友情を育み、仲間と力を合わせる経験を積む場を提供することが大切です。
学んだことを生かして遊びの幅の広がりや工夫が生まれ、遊びを通してできた仲間とのつながりを生かした「学び合い」が生まれる――。「健康な英才主義」と「人間性豊かな実力主義」という教育方針のもと、遊びと学びが互いに影響し合う中で、子どもたちが友情を広げ、興味関心を追求する姿勢がより育まれることを実感しています。これは、子どもたちが自信をつけ、実力を兼ね備えた人への成長に繋がっていくと信じています。

「学ぶ喜び」は大人の「楽しむ心」から
子どもが心から楽しみ、いきいきと学ぶ。そして、子ども自身の可能性を最大限に引き出す。東京創価小学校が目指す「明るい子」「思いやりのある子」「ねばり強い子」の育成のために、大人ができることはなんだろうか。
学校現場で遊びを学びにするという挑戦は、「子どものためにできることは何でもしたい」という創立者池田先生の思いを受けた教員の純粋な気持ちから始まったのかもしれない。それは、子どもたちが自信をつけ、実力を発揮できるようにという、私たち教員が常に心に抱いている教育方針の実践でもある。
そして、子どもが心から楽しむためのもう一つの大切な条件。
それは「大人も子どもと一緒に心から楽しむこと」だと考えている。
大人の「楽しい」と思う気持ち、「わくわくする」という気持ちが子どもにも伝わり、普段の「創価の対話による学び合い」の授業がそうであるように、子どもが感じる「学ぶ喜び」に通じていくと信じている。大人が率先して楽しみ、子どもたちに学びに挑む姿勢を示すことで、子どもたちの学ぶ意欲はさらに高まっていく。
